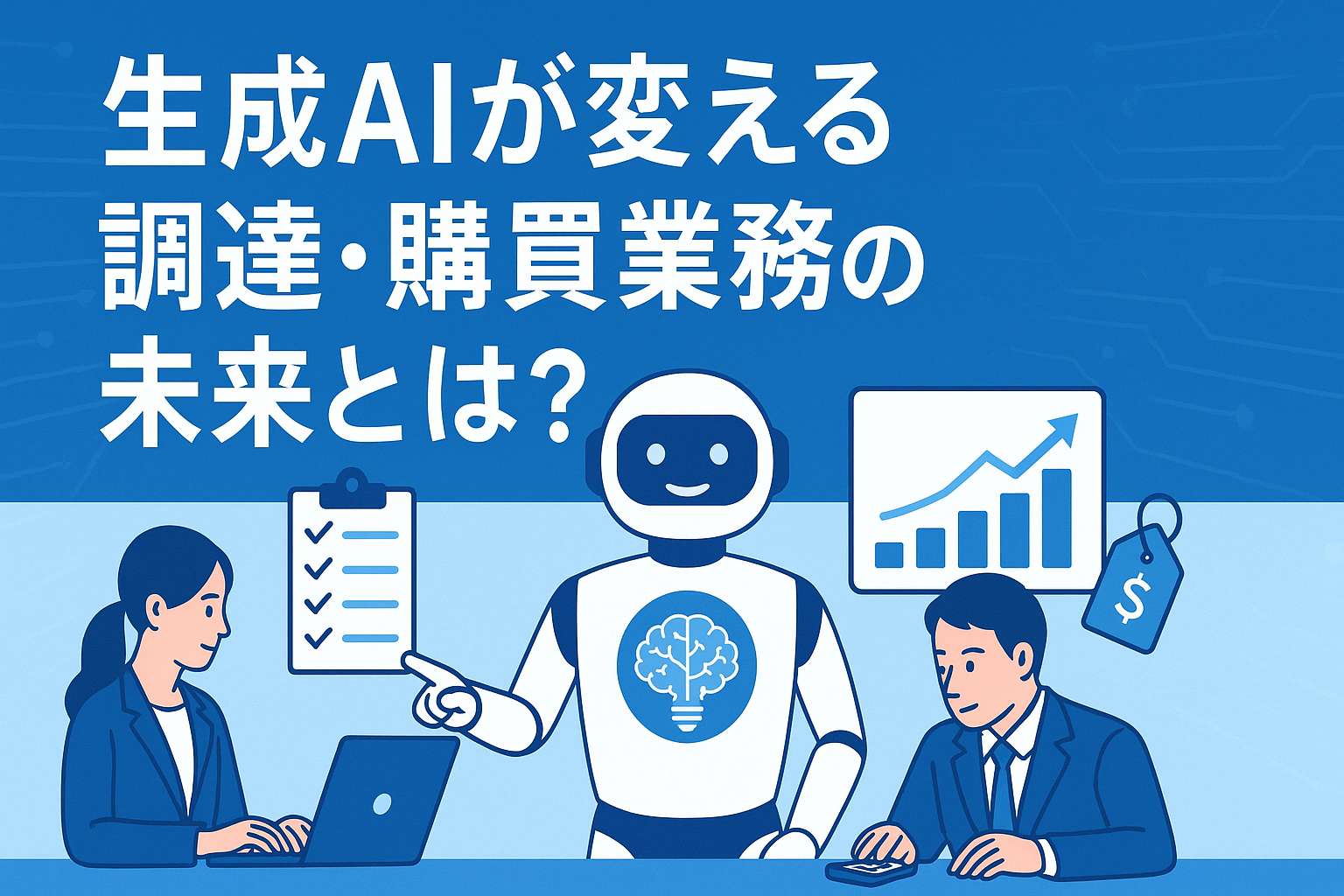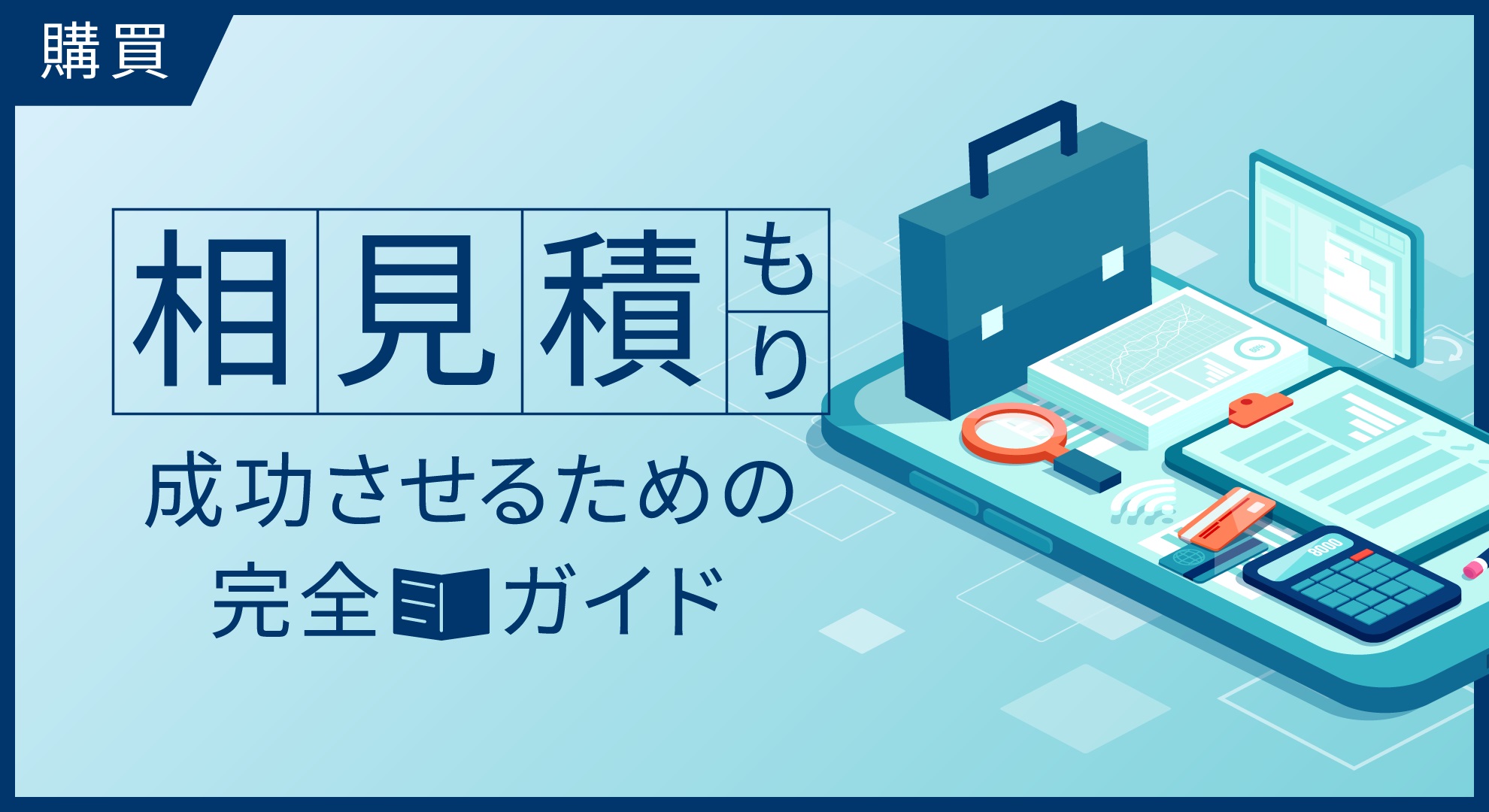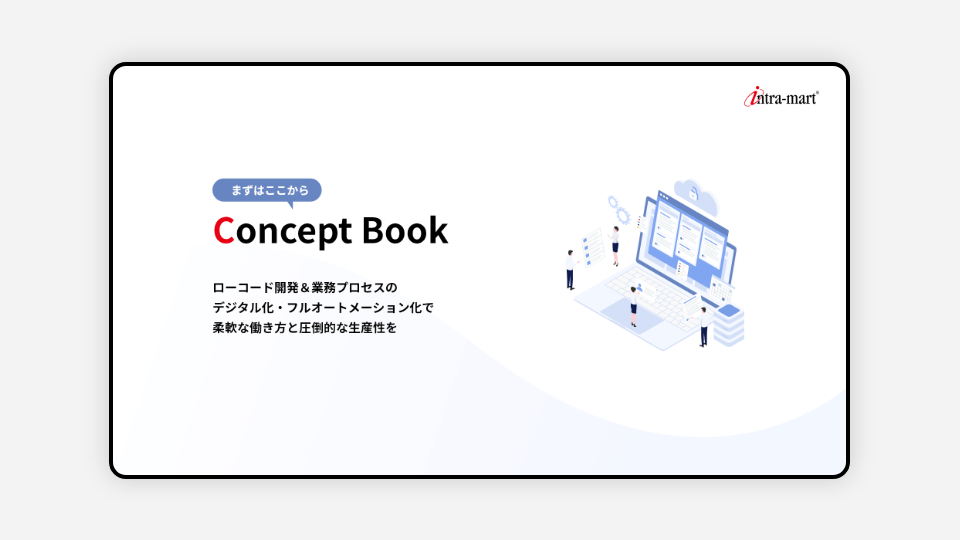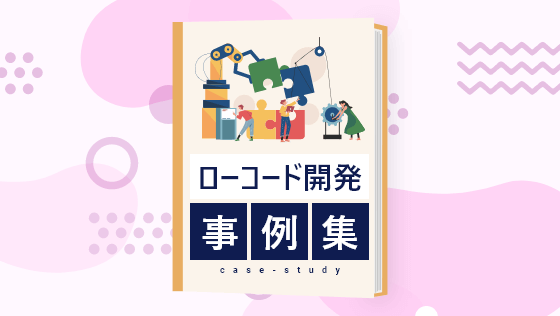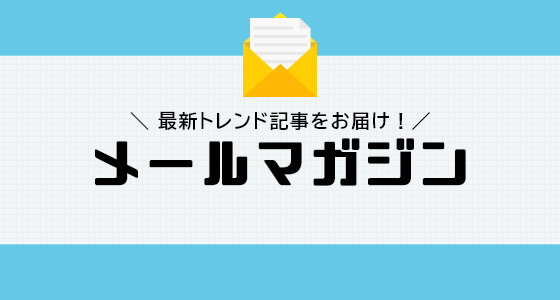サプライチェーン最適化とは?業界別の取り組み事例もチェック
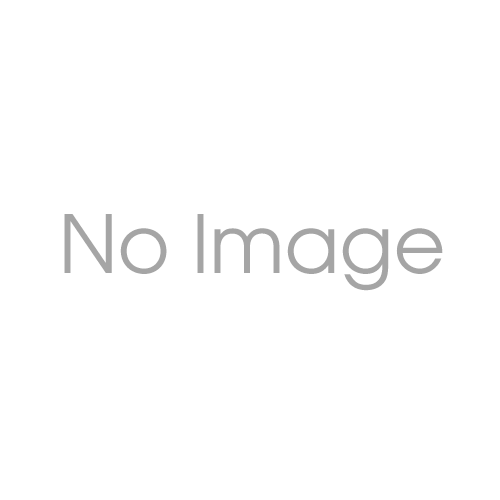

サプライチェーン最適化とは、商品の製造から販売までの流れ(サプライチェーン)におけるムダを省いて効率化を試みる取り組みをいいます。
しかし「取り組むことで具体的にどのようなメリットが得られるのか」「実際にどのような取り組みがされているのか」などについて、おおまかなイメージしかない方もいらっしゃるでしょう。
この記事では、サプライチェーンやサプライチェーン最適化について、取り組み事例・メリット・課題などについてわかりやすくご紹介します。
スムーズかつきちんと効果の出る形でサプライチェーン最適化に取り組みたい方は、ぜひご覧ください。サプライチェーン/サプライチェーン最適化とは?
サプライチェーンとは、原材料の調達から製品が消費者へ届くまでに辿る、一連の供給プロセスを指します。
製造に携わる企業それぞれの垣根を越えた、全体的な製造フローともいえるでしょう。
なかでも、サプライチェーンに海外拠点や海外企業も含む場合は「グローバルサプライチェーン」とも呼ばれます。
一方「サプライチェーンの最適化」は、製造にかかる一連の流れにおいて、ムダを省いて業務効率を高めることをいいます。
ただし、最適化の際に注目すべき情報は、コストだけではありません。
下記のことを含め、顧客満足の向上・リスク低減・業務の標準化などの視点をもってさまざまな面から最適化を試みる必要があります。
- 在庫管理の効率化
- リードタイムのさらなる短縮
- 高品質な製品の提供体制
- 想定される各種リスクに対する、バックアップ戦略の策定
サプライチェーン最適化は、サプライチェーンマネジメント(SCM)と呼ばれる手法で行われます。
SCMはシステムを用いてモノ・コストの流れを管理して、関係企業・部署へ共有し、最適化を図るものです。
取り組みを成功させるには、自社を含めた一連の供給プロセスを俯瞰し、改善点を見つける広い視野と知識が求められます。
サプライチェーン最適化が注目されている理由
サプライチェーン最適化が注目される理由として、グローバル化・人手不足・デジタル技術の進化・顧客ニーズの多様化などが挙げられます。
・グローバル化による要因
国をまたがって展開されるサプライチェーンが増えたなかで、市場競争で勝ち残るためには、適正価格に基づいたスピード感のある供給体制の整備が不可欠となりました。
また、グローバル化により、サプライヤー側の自然災害・地政学的リスク・政治的要因など、サプライチェーンに大きな影響が生じるリスクが生じやすくなるという事情もあります。
・人材不足による要因
2024年問題や少子化にあるように、製造や運送へ携わる人的リソースが減少していることも関係しています。
省人化できる箇所は省人化し、人材不足の課題を解消しながら、持続可能なサプライチェーンのありかたを実現するために注目されているのです。
・デジタル技術の進化による要因
需要予測にもとづいた生産調整やタイムリーな製品供給などがデジタル技術の進化によって実現されています。
技術を最大限に活かすために、スピーディなデータの入力・管理・共有が必要とされています。
・顧客ニーズの多様化による要因
顧客ニーズの多様化により、多種多様な製品の生産が必要とされたり、一つのアイテムのライフサイクルが短くなったりするなどの変化が生じました。
こうした状況に対応するために、サプライチェーンの効率化による迅速な管理が必要とされています。
サプライチェーン最適化のプロセス
サプライチェーン最適化のプロセスは、見直しとPDCAの2段階にまとめられます。
見直し段階では、サプライチェーン全体の現状を把握する必要があります。
関係企業・拠点の位置・在庫状況・リードタイム・コストなどを詳細に分析し、課題や改善点をピックアップしましょう。
課題とは、工程のボトルネック・非効率なルート・過剰在庫・品質や仕入れ先の問題などです。
そして、課題に対する改善策に沿って、PDCA(計画→実行→評価→改善)を回します。
見直しの際は膨大なデータの分析をもとに計画を立案する必要があるため、システムやAIを利用し、できるだけ多くの選択肢を効率的にシミュレーションして確認することが重要です。
シミュレーションにより効果的と判断できる計画が立案できたら、実際に反映させてみましょう。
実際に運用してみた結果をもとにPDCAサイクルを循環させ、トライアンドエラーでさらなる最適化を目指します。
サプライチェーン最適化のメリット
SCMによってサプライチェーン最適化を成功させると、3つのメリットを得られます。
利益率の改善に役立つ、下記のメリットを確認しておきましょう。
- 情報の一元化が実現する
- 在庫・運送・スケジュールにおけるムダを削減し効率化を狙える
- BCPの取り組み|柔軟性がある確かな製造を実現できる
情報の一元化が実現する
サプライチェーン最適化では、企業の垣根を越えて情報を収集・整理し、一元化する必要があります。
情報がまとまれば企業間のコミュニケーションが改善され、よりスピーディかつ強固な製造体制を実現できるでしょう。
情報の一元化により、自社内でサプライヤーを統一して、品質の高い仕入れ先から過不足なく安定的に製品を仕入れられるようになります。
結果的には、自社の購買の効率化に加えて、製品の品質の向上や安定にもメリットを感じられるでしょう。
情報を整理・集積することで、データをもとにした分析やPDCAサイクルの実施などをしやすくなるのも大きなメリットです。
在庫・運送・スケジュールにおけるムダを削減し効率化を狙える
需要動向に基づく適切な在庫管理がなされれば、過不足によって生じるムダを省けます。
その結果、リードタイムの短縮・管理コスト削減にもつながります。
典型的なケースとして、「欠品対策のために多く発注をした結果、在庫が過剰になりロスが生じてしまう」といった例は、サプライチェーンの効率化によって改善可能です。
システムを活用して情報を分析することで、運送スケジュールやリードタイムの削減も可能です。
「経由地点や順路にムダがないか」「経由地点での待機時間がどれくらいか」「生産体制を見直してリードタイムを短縮できないか」などをチェックし、さらなる効率化を図りましょう。
さらに、システム活用により正確性の高い需要予測が得られれば、発注数が最適化され運送量を減らせます。
運送コストを削減したり、より必要な箇所へ人員を派遣できたりすることで、よりサプライチェーン全体の効率化を目指せます。
BCPの取り組み|柔軟性がある確かな製造を実現できる
BCP(Business Continuity Planning:事業継続計画)の観点でも、サプライチェーンマネジメントの最適化は重要です。
サプライチェーン最適化に取り組み情報を一元化しておけば、災害・パンデミック・ストライキ・政治・軍事・地理その他を原因とする緊急事態に陥っても、すぐに代替案を見つけて指示出しができるでしょう。
とくにグローバルサプライチェーンを展開している場合は、拠点の切り替え、迂回路の指定、人的リソースのカバー方法などの選択肢が多いため、情報をすぐに確認できるようにしておくことが大切です。
サプライチェーン最適化を図って情報を一元化しておくことで、供給路が寸断されるリスクを減らすとともに、販売機会の喪失を最小限にとどめられるでしょう。
サプライチェーンとその他の概念の違い
「サプライチェーン」ということば・概念は、主に製造・物流・小売などの業界で用いられています。
しかし同様に用いられる「バリューチェーン」や「ロジスティクスチェーン」との違いがわからない、とお悩みの方もいらっしゃいます。
それぞれの概念の違いについておさえておき、スムーズなやりとりができるようにしておきましょう。
バリューチェーンとは
バリューチェーンとは、製品の付加価値を高める取り組みをいいます。
製品が顧客へ届くまでの流れにおいて、自社の強み・弱み・改善点などを分析するために用いられる概念です。
コスト・生産性などを分析し、自社製品が支持されるポイント(価値)を知り、競争力を高めることを目的としています。
サプライチェーンは付加価値ではなく、モノの流れへ目を向ける取り組みです。
製品の動き・流れに注目し、数・時間・コストなどの最適化を図る点に違いがあります。
ロジスティクスチェーンとは
ロジスティクスチェーンは物流に限定した概念で、リードタイムの削減や運送企業における作業効率アップのため重視されています。
原材料の製造に携わるメーカーと加工工場、工場から小売店など、流通上の効率化を目指す取り組みです。
2024年問題により、運送に携わる人材が不足する課題が生じたことで、ますます注目を集めています。
一方でサプライチェーンも、製造から消費者へ届くまでの工程における効率化を狙うという点は同じです。
ただしリードタイムの削減だけでなく、供給量の最適化、コストの最適化など、流通・運送以外の視点も含まれる点が異なります。
サプライチェーン最適化の業界別事例
SCMを用いたサプライチェーン最適化について把握できたところで、業界別の事例を確認してみましょう。
ここでは、小売・ライフケア・アパレルから3事例をご紹介します。
それぞれ確認し、自社ではどのような取り組みができるか、具体的な案を作成しておきましょう。
小売|経済産業省・コンビニエンスストア
経済産業省と大手コンビニエンスストア3社(※1)は、2022年、戦略的イノベーション創造プログラム「スマート物流サービス」プロジェクトとして、サプライチェーンを横断した共同物流の実証実験に着手しました。
※1・・・株式会社セブン-イレブン・ジャパン、株式会社ファミリーマート、株式会社ローソン
実証実験では、物流の効率化を通じて「運行トラックの削減」「温室効果ガス排出量の削減」「食品廃棄の削減」などによる、持続可能なビジネスモデルの作成を試みました。
具体的な内容は、下記のとおりです。
- 基幹センター・サテライトセンター間における横持ち配送の共同化実証を通じた、物流コストの削減
- 遠隔地店舗・買い物困難地域への配送共同化
これにより、1.では運送距離で48%、温室効果ガス排出量で45%、運送時間で23%の改善効果が確認されました。
2.では、運送時間で20%、運送距離で22%の改善効果を確認しています。
運送距離・時間の短縮と、それにともなう温室効果ガス排出量の削減を実現でき、最適化による効果が確認されました。
詳しくはこちら:経済産業省「大手コンビニ3社の地方における共同配送の実証実験を実施します~物流課題の解決に向けて~」
ライフケア|花王株式会社
ライフケア製品の製造・販売を担う花王株式会社では、ヒト・社会・地球にやさしい循環型サプライチェーンを目指し、下記のような最適化への取り組みを実施しています。
- 循環オリコンを複数企業間で共有し、仕様差異から生じる障壁を撤廃
- 共同物流による輸送最適化。荷待ち時間の削減を通じ、環境負荷を削減
- 共同倉庫の活用による、保管・輸送コスト削減
- 配送から陳列までカバーできる「ぐるぐるBOX」の活用による、店頭作業の効率化
- 仕分けロボット・無人搬送車・自動運転フォークリフトなどを活用する、生産・物流機能一体型拠点への変革、新たな物流モデル構築
花王株式会社では運送業務に各種システムを取り入れ、外部メーカー・パートナー企業とも協働し、フレキシブルなロジスティクスの実現を目指して取り組んでいます。
さらに、ビジネス視点(購入額、代替原料の置き換え可否)、エリア視点(所在地に関連するリスク)、ESG(環境・社会・ガバナンス)視点におけるハイリスクサプライチェーンの特定と、本質的解決へ向けた取り組みも実施。
直接的な取引先はもちろん、間接的にかかわる広義的なサプライチェーン企業をも対象に、リスクの把握と解決へ向けて取り組んでいます。
アパレル|株式会社ファーストリテイリング
ユニクロやGUを展開する株式会社ファーストリテイリングも、サプライチェーン最適化へ本格的に取り組む企業のひとつです。
リードタイム削減や在庫の最適化について、データの一元化・可視化を通じて下記の取り組みを実施しています。
|
取り組み例 |
|
|
リードタイム削減 |
3D-CADの導入 |
|
在庫の最適化 |
AI・アルゴリズムによる販売計画の精微化 |
サプライヤーのサプライヤー、4つ先のサプライチェーン企業までを対象に、改革を実施しています。
製造業におけるサプライチェーン最適化・SCMの課題
サプライチェーン最適化やSCMの実施は、コスト削減やリードタイム短縮において大きな効果を発揮し、企業活動のサステナビリティを大きく向上させます。
しかし、サプライチェーン最適化・SCMに取り組もうとするときは、3つの課題に直面するでしょう。
下記の課題について、ひととおり把握したうえで取り組むことが大切です。
- サプライチェーン最適化のために扱うデータが膨大
- システムを導入するにはコストがかかる
- サプライチェーン最適化のために多くの時間を費やす必要がある
扱うデータが膨大
サプライチェーン最適化にあたっては、取引先の取引先までを含めてデータを分析し、課題を特定したうえで、根本的な解決策の立案・実施に取り組む必要があります。
たとえば、各工程にかかわる拠点、製造や運送にかかるデータ、販売時点での在庫・廃棄データなど、膨大なデータを分析して最適化を図ることになるでしょう。
自社内の業務効率化を狙うだけでも多くのデータを扱う必要がありますが、サプライチェーン全体で統一的に取り組む場合はさらに膨大なデータを処理しなければなりません。
手作業だけでは処理しきれず、システム・AIを活用する必要性が生じるでしょう。
導入にはコストがかかる
最適化を狙うにあたっては、サプライチェーン全体で情報を共有したりリアルタイムで更新できたりするシステムや、サプライチェーン最適化に特化したSCMシステムを導入すると効率化を図れます。
SCMシステムは主に下記の機能を搭載しているため、導入すれば、各工程における効率化への取り組みをスムーズに進められるでしょう。
- 需要予測機能
- 在庫管理機能
- 仕入れ管理機能
- 生産計画機能
- ロジスティクス管理機能
ただし、SCMシステムやAI・システム・ツールを導入する場合は、まとまったコストが必要です。
サプライチェーンに加わっている企業が多いほど、あるいは自社独自のシステム・カスタマイズ性の高いシステムを作成しようとするほど、コストがかさんでしまうでしょう。
初期費用・ランニングコストともにかかるため、よく比較して導入システムを決める必要があります。
多くの時間を費やす必要がある
サプライチェーン最適化に際しては、関係する企業それぞれが、垣根を越えて意思統一・協働することが不可欠です。
各企業の経営における重要な情報も共有する必要があるため、相互的な信頼関係を構築しなければなりません。
また膨大なデータを整理しつつ共有・分析し、改善の施策を立案し実行するには、多くの時間を費やすことになる点も課題となるでしょう。
コスト面で不安がある場合は「intra-mart Procurement Cloud」をご検討ください
サプライチェーン最適化に着手したいものの、システム導入にかかるコスト負担、データ分析のリソース確保など、課題が多くて厳しいと感じた方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そのときは、企業間取引をワンストップで一元化できる「intra-mart Procurement Cloud」をご検討ください。
「intra-mart Procurement Cloud」は、ソーシングから支払いまでの情報をまとめ、効率化を目指せるクラウド型の調達・購買システムです。
調達管理機能・購買管理機能・カタログ購買機能など、支出の最適化、調達・購買業務の効率化などに役立つ機能を備えています。
システムの導入により、ペーパーレスで購買や支払に関する業務を一元管理できるだけでなく、サプライヤーとの関係性強化にもつながる機能を搭載しています。
例えば、頻繁に発注するアイテムについてはカタログ化して、購買側と供給側の業務負担の軽減が可能です。
購買業務に加えて、サプライヤー情報の管理や社内の承認フローの効率化のメリットも実感していただけるでしょう。
「intra-mart Procurement Cloud」はクラウド型かつ1部署1品目のスモールスタートにも対応しており、コスト負担も軽減しながら導入できます。
また、資料請求や調達DX診断、デモンストレーションにも対応。
サプライチェーンにおける業務の効率化を狙いたい場合は「intra-mart Procurement Cloud」から、ぜひご確認ください。
まとめ
サプライチェーン最適化とは、原材料の調達から製品が消費者へ届くまでに辿る供給プロセスからムダを省き、効率化・利益の最大化を図る取り組みをいいます。
システム導入・DX化・AI活用などを通じ、各サプライチェーンで積極的に試みられている取り組みです。
ただし実施に際しては課題もあり、慎重な検討が必要です。
ご紹介した内容をもとに、適切なシステムを導入し、最適化を図ってみましょう。